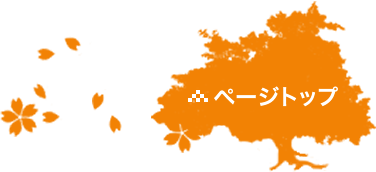TOP > ピックアップコンテンツ > 岡山県医師会の歴史 > 松山正春 会長時代
岡山県医師会の歴史
17 松山正春 会長時代(2018年6月~ )
<第1次松山正春執行部・2018年6月~2020年6月>

第1次松山正春執行部が2018年6月17日、発足した。石川前会長の後を受け、第17代会長に就任。副会長に清水信義、大原利憲両氏、専務理事に神﨑寛子氏が就いた。常任理事(新設)・理事計15人のうち9人が新任で、フレッシュな陣容となった。新執行部は4月22日、任期満了に伴う次期執行部を選出する第193回岡山県医師会臨時代議員会で松山副会長が無投票で会長に選出されていた。
任期中の大きな出来事は、西日本豪雨による倉敷市真備町の水害と新型コロナウイルスパンデミック。新執行部発足3週間後の7月6日深夜から7日未明にかけ、線状降水帯による豪雨で小田川が氾濫、倉敷市真備町が水没、死者も多数出るという大災害が発生した。松山会長はJMATおかやまを編成していち早く、現地へ派遣した。一方、パンデミックとなった新型コロナウイルスには、研修会開催、PCR検査場へ医師派遣、夜間集団接種など県医師会の総力を挙げて対応した。
一方、松山会長は、新規の事業として「移動会長室事業」をスタートさせた。ACP普及、フレイル対策、受動喫煙防止をテーマに柱として、会長自ら県内各地を巡り、その普及・啓発に努めた。
- 会長
- *松山正春
- 副会長
- 清水信義、*大原利憲
- 専務理事
- 神﨑寛子
- 常任理事
- *内田耕三郎、佐藤正浩、合地 明、藤本政明
- 理事
- 國富泰二、田淵和久、*太田隆正、*石井純一、*宮本 亨、*大橋 基、*榊原 敬、*尾﨑敏文、*名越 充、*平木章夫
- 監事
- *中島豊爾、*松下 睦
(*は新任)

県医師会に常任理事制を導入
県内各地域の意見を吸い上げることを狙いに松山新体制から常任理事制が導入された。石川前会長当時からの懸案事項で、県内5ブロック医師会代表などから選出された理事らと常任理事の体制。毎週開かれる常任理事会で重要案件などを決定、月1回開かれる理事会等で事案を報告・諮る制度とした。
ミャンマー医学生研修支援(4月)
県医師会が、国際貢献の一環として資金援助を行い岡山大学医学部・同大学病院で研修中のミャンマー医学生10人が2018年4月19日、木股、竹居両岡大教授、岡田岡大名誉教授(日本・ミャンマー医療人育成支援協会理事長)ともに表敬訪問した。学生たちは母国の医療の将来を担う人材で研修の成果が期待される。
西日本豪雨で真備町水没。JMATおかやま派遣
西日本豪雨により小田川とその支流の堤防が決壊、7月6日深夜から7日未明にかけ、地域の三分の一が水没、死者52人を出した倉敷市真備町。同エリアにある医療機関も12施設のうち11病院・診療所が被災した。岡山県医師会では8日、松山会長を本部長とする災害対策本部を急きょ立ち上げ、JMATおかやまの編成を検討。12日の第一陣を皮切りに現地での救援活動を展開した。県外JMAT、吉備医師会、倉敷市連合医師会などと連携し、一人JMATを含め、8日から31日まで県外JMAT延べ106(24日で撤収)、JMATおかやま延べ133、計延べ239チームが仮設診療所や各避難所で医療活動を行った。松山会長は連日、倉敷市保健所に設置された医療支援活動の司令塔「倉敷地域災害保健復興連絡会議」(KuraDRO)で陣頭指揮に当たった。

水没した真備町(2018年7月7日午後2時40分頃撮影)

真備町・薗小学校の避難所の様子(2018年7月20日撮影、倉敷市提供)

真備町の避難所での診療=薗小学校
禁煙推進部会発足(8月)
2020年の東京五輪を控え、受動喫煙防止の機運の盛り上がりを背景に、県医師会に禁煙推進部会(部会長・清水信義副会長)が2018年8月21日、設立された。子供らをたばこの害から守ろうと禁煙教育の実施や県独自の受動喫煙防止条例制定に向け、運動を強力に推進していく。2019年5月23日には岡山市民会館で大規模な県民総決起大会を開くこととした。
移動会長室「会長がゆく! 虹色サロン」 (9月~)
広く県民に県医師会の活動を知ってもらおうと新たに「移動会長室事業」を始めた。その柱の一つである「会長がゆく! 虹色サロン」は、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)がテーマ。終末期を含めた医療や介護について本人、家族らと話し合うことの必要性について地域のリーダーらと会合を持ち、理解を深めてもらっている。9月13日、御津医師会エリアを皮切りに倉敷、津山、岡山、新見、西大寺、玉島で順次行った。2019年度からは、対象を高校生にも拡大、明誠学院、金光学園、津山高で開催した。
2019(平成31・令和元)年
フレイル対策事業(1月から)
「移動会長室」事業の柱の一つである「けんこう長寿教室」のテーマは、フレイル対策。県民の健康寿命の延伸を目的とし、松山会長、名越理事が県内の各医師会、行政と協力して開催。1月の浅口会場を手始めに2月高梁、津山、3月新見で実施、フレイル、ロコモへの認知度を深めてもらった。循環器・呼吸器疾患や認知症などの早期発見・治療、運動器障害が要介護の原因となることを解説するとともに理学療法士が参加者に筋肉強化の運動指導を行った。
ミャンマー医学生表敬訪問(4月)
国際貢献の一環として県医師会が資金援助を行い、岡山大学医学部・同大学病院で研修中のミャンマーの医学生男女11人が2019年4月17日、木股、竹居両岡大教授、岡田岡大名誉教授(日本・ミャンマー医療人育成支援協会理事長)とともに表敬訪問した。出迎えた松山会長、清水副会長らに研修の印象など話した。医学生は約3週間、基礎病態を学んだほか、ラボ演習などを行った。
代議員会議長に福嶋氏、副議長に滝澤氏選出(4月)
第195回岡山県医師会臨時代議員会が4月21日開催され、議長に福嶋啓祐氏(浅口)、副議長に滝澤貴昭氏(赤磐)が、無投票でそれぞれ選出された。
県医師会報1500号発刊(4月)
岡山県医師会報が2019(平成31)年4月25日号で1500号を迎えた。これを記念して「1500号記念特集号」を刊行。医師会報は、1947(昭和年22)年、新生医師会が発足後の1950(昭和25)年3月1日、第1号を発刊して以来、69年にわたり号を重ねてきた。1500号は丁度、平成最後の月と重なり、改元された令和元年5月が1501号となった。これを機に、会報サイズをB5判からA4判に一新、表紙も面目を新にした。
受動喫煙防止県民大会(5月)

“頑張ろうコール”で気合を入れる参加者=岡山市民会館
岡山県独自の受動喫煙防止条例の制定を目指し、機運を盛り上げよう、と受動喫煙防止県民総決起大会が5月23日、岡山市の岡山市民会館で医療関係者、県民ら約1000人を集めて行われた。専門医によるたばこの害や禁煙支援などの講話、県民からのメッセージ、医療関係団体の決意表明を行った。「決議」採択し、頑張ろうコールで締めくくった。
第196回岡山県医師会定例代議員会で専門医研修のシーリング見送り決議
標記代議員会が6月16日開かれ、厚労省・日本専門医機構が都道府県医師会に示した2020年度専門医研修プログラムで診療科別のシーリングが設定されたことに対し、「専攻医の教育・研修の場が奪われる」として、その実施を見送ることを決議した。
岡山県受動喫煙防止推進協議会が、受動喫煙防止条例制定を知事に要望
標記協議会(岡山県医師会など86団体・清水信義代表世話人)有志が9月4日、県庁を訪ね、県独自の受動喫煙防止条例を制定するよう伊原木知事と蓮岡県議会議長に要望書をそれぞれ手交した。
3.6万人の署名簿も提出。
令和元年度がん征圧岡山県大会
がん征圧岡山県大会が9月2日、県医師会館三木記念ホールで開催され、がん征圧事業功労者表彰などのほか、日本対がん協会の垣添忠生会長が「がん予防と検診の大切さ」の演題で講演した。
RSKテレビで子宮頸がんワクチン接種呼びかけ
がん征圧月間活動の一環として、田淵和久理事が9月6日、RSKテレビに出演、子宮頸がんについて解説。国は未だ勧奨を中止したままだが、「ワクチンで発症が防げるのでぜひ接種を」と呼びかけた。
ピンクリボン岡山チャリティーコンサート
乳がんの正しい知識の普及と検診を啓発する標記コンサート(ピンクリボン岡山実行委員会・県医師会主催)が10月14日、県医師会館三木記念ホールで行われ、市民ら約130人が参加した。医師らで編成されたバンドやグループが見事な演奏を披露、会場では多くの“善意”が寄せられた。寄付者にはピンバッジやタオルが贈られた。今回で4回目。
糖尿病県民公開講座
標記講座が11月4日、県医師会館三木記念ホールで開催され、県民約300人が聴講した。特別講演として、東京女子医大の馬場園哲也教授が「透析導入を回避するために何をすべきか」のテーマで話した。
国民医療・介護を守るための総決起大会
来年度の診療報酬改定を控え、県医師会などで構成する岡山県国民医療・介護推進協議会主催の標記大会が12月4日、岡山市の岡山市民会館で開かれ、医療・介護関係者約1000人が参加。国民皆保険の堅持と持続可能な社会保険制度の確立に向け、適切な財源確保を国に要望することを決議した。
2020(令和2)年
石川 紘前県医師会長が山陽新聞賞受賞
1月3日発表された第78回山陽新聞賞で、前県医師会長の石川 紘氏が受賞(社会功労部門)した。氏は、県医師会の理事、副会長、会長(3期)を務めるなど四半世紀にわたり医師会活動に邁進、地域医療の発展に貢献した。
第197回県医師会臨時代議員会で選挙に関する定款改正承認
標記代議員会が1月25日開かれ、選挙に関する定款と施行規則の改正を審議、承認された。備前、備中、美作、岡山、倉敷の5地区代表理事の当選を担保することが狙い。
県医師会新型コロナウイルス感染症対策本部設置
新型コロナウイルスの流行に備え、松山会長を本部長とする対策本部が、県医師会に2月5日開設された。県や日医から提供されるコロナ情報を郡市等医師会、会員らへ提供する体制を整備した。
中国・武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症が同国で爆発的に流行、2月4日には東南アジアなどを周遊して横浜港に帰港した大型客船・ダイヤモンドプリンセス号の乗客の感染が判明するなどパンデミックの兆しを呈していることを受けて、いち早く設置した。
第4回JMATおかやま研修会
災害時にJMATとして医療活動を行うために必要な知識と技能を習得するため標記研修会が、川崎医科大学附属病院救急科と共催で2月23日、川崎リハビリテーション学院講堂で開かれ、医師ら約50人が参加して座学と実習を行った。
「女性の健康週間 県民公開講座」規模縮小し開催
標記講座が2月24日、「耳鳴り・めまい・難聴」をテーマに県医師会館三木記念ホールで約360人が参加して行われた。新型コロナ感染対策のため、プログラムを変更・短縮して開催した。
会議、行事の中止・延期相次ぐ(2~3月)
新型コロナウイルス感染症が拡大、経済、スポーツ、文化・芸能など様々な分野で影響が出始めている中、2~3月に予定されていた県医師会主催の「第11回岡山県民公開シンポ」「第7回CKD県民公開講座」、「会長がゆく! 虹色サロン」など軒並み中止、さらに拡大の様相。3月28、29日予定されていた日本医師会代議員会も中止。2月27日には安倍首相が全国の小・中・高校に3月2日から春休みまで臨時休校を要請、波紋広がる。
「岡山県医師会災害医療救護マニュアル」発刊
県医師会は3月、標記マニュアルを新たに発刊、会員へ配布。2008年に作成した「岡山県災害医療救護手引書」が、その後、2018年西日本豪雨災害で真備町が被災し、「JMATおかやま」を編成・派遣するなど災害医療の様相が大きく変わったことを受け、全面改訂した。
「子ども予防接種週間」ラジオ・新聞で接種呼びかけ
子ども予防接種週間(3月1~7日)に合わせ、ラジオ・新聞のスポット広告のほか、担当の國冨泰二理事がラジオや新聞で定期接種を呼びかけ。風疹についても、CRS予防のため「無接種世代の男性はワクチン無料接種出来ます」とPR。未知の感染症・新型コロナについても「SARSほど危険でない、怖がり過ぎず手指消毒など予防策を」。
WHO「パンデミック」宣言受け、TVで新型コロナ解説
WHOが「パンデミック」を宣言した翌日の3月12日、標記番組で感染症に詳しい國冨泰二理事が緊急出演、未知の感染症・新型コロナについて解説した。「高齢者や持病のある人はハイリスク。まだ特効薬や予防接種はないので、マスク着用、手指消毒、3密回避を守って」と呼びかけた。
新型コロナウイルス感染症対策講演会
県医師会は3月21日、標記講演会を県医師会館三木記念ホールで開いた。講師に招いた長崎大学熱帯医学研究所の山本太郎教授が、新型コロナウイルスとSARS・MERSとの違い、スペイン風邪・ペスト流行の過去のパンデミックについて講義。
岡山県で新型コロナウイルス感染初確認
3月22日、スペイン旅行から帰国した60代女性のコロナ感染が確認された。岡山県で初めて。
OHK「なんしょん?」で新型コロナ解説第2弾
松山正春会長が3月30日、同番組に出演、新型コロナウイルスへ注意を喚起した。早期のワクチン開発を願う一方、「感染者の感染源不明が心配。若者は無症状でも、動き回ることで重症化しやすい高齢者に感染させる恐れがあることを知ってほしい」と訴えた。前日の29日、コメディアンの志村けんさんがコロナで急死した。
県医師会新型コロナウイルス感染症相談センター開設
県医師会新型コロナウイルス感染症相談センターを4月1日開設。保健所へのPCR検査依頼が不調に終わった場合の救済措置として、県保健福祉部と相談して、検体採取可能な医療機関を紹介することとした。
国から支給のマスクを郡市医師会に配布
新型コロナ感染の急拡大で品薄となっているマスクの政府支給分が4月1日、県を通じて岡山県医師会に届き、郡市医師会へ計84,560枚が支給された。
OHK「なんしょん?」で新型コロナ解説第3弾
松山正春会長が4月7日、先週に続き同番組に出演、緊迫する新型コロナウイルスに関し、県内の感染状況(12例目)、医療体制、感染防止策の徹底などを訴えた。
7日夜、安倍首相が7都府県に「緊急事態宣言」発令した。
岡山シーガルズにAED寄贈
県医師会が4月15日、バレーボールのシーガルズにAED1台を寄贈した。今回で2度目。吉田みなみ主将らが県医師会館を訪れ、松山会長から手渡された。
第198回県医師会臨時代議員会で次期会長に松山会長再選
標記代議員会が4月19日、県医師会館三木記念ホールで開かれ、松山正春会長が無投票で再選された。新執行部は、6月の定例代議員会終了後に正式発足。
県医師会が緊急記者会見(第1弾) 「GWの連休は外出自粛を」
コロナ感染が拡大する中、県医師会は5月の大型連休を控えた4月24日、県医師会館で記者会見を開き、松山会長が「感染の連鎖を断ち切るため、連休中は家族と家で過ごしましょう。今、県民の賢さが問われています」と強く訴えた。在岡マスコミ13社が出席した。
松山会長は、岡山県の感染者数が24日現在で19人、10万人当たりでは全国で下から5番目であることから、「県民の公衆衛生意識が高いことやかかりつけ医の啓発努力のお陰」とした。
一方で「高齢者施設などは、一旦クラスターが発生すると一気に感染が拡大、多くの死亡者が出ることが予想される」と危惧を示すとともに、「感染者の8割が無症状あるいは軽症であるため、若い人は感染を自覚しないまま広範囲に出歩き、感染を拡散させる危険がある。不要不急の行動を控え、密閉・密集・密着の“3密”はぜひ回避して頂きたい」と注意を喚起した。
さらに、医師やその家族が誹謗中傷を受けていることを報告。「医師ら医療関係者は、危険と隣り合わせで、懸命に診療に当たっている。ぜひ感謝と温かい励ましの言葉を掛けて頂きたい」と訴えた。
報道陣にPCR検査採取作業を公開
PCR検査体制の増強が急がれる中、県医師会は、4月30日、報道陣に同検査用の検体採取の作業を公開した。5月1日に県が、岡山市に屋外PCR検査場を開設するのに先立ち、県、県看護協会と協力し実施。清水信義副会長が、仮設の採取ボックスのアクリル板に設置された防護手袋で、綿棒を使い患者の鼻から粘液を採取した。
医師会報5月10日・25日号は合併号
新型コロナウイルス感染症拡大により、医師会報5月10日・25日号は合併号(25日発行)とする。会議、行事等が軒並み中止・延期となったための緊急措置。
岡山南ロータリークラブが県医師会に1千万円寄付
新型コロナと闘う医師に感謝を込め―岡山南ロータリークラブが5月13日、県医師会に1千万円を寄付した。伊澤正信会長が県医師会館を訪れ、「感染の危険にさらされながら懸命に診療に携わる医療関係者を、今こそ支援する時」と松山会長に贈った。
岡山商工会議所が400万円寄付
新型コロナと闘う医療者を応援しようと、岡山商工会議所が5月20日、県医師会に400万円を寄付した。松田久会頭は、「今はまず医師を支援しなければ」と松山会長に手渡した。
三菱自動車水島はフェースシールド寄贈
三菱自動車水島も5月20日、自社製のフェースシールド200個寄贈。
タイオン奨学金からマスク寄贈
タイオン奨学基金が5月28日、県医師会へマスク7万枚寄贈。
禁煙週間で会長、知事懇談
禁煙週間を迎え、松山会長、西井研治県健康づくり財団附属病院長は6月3日、伊原木知事、県保健福祉部長らを訪ね、新型コロナウイルスと禁煙の関係などについて意見交換した。
会長は、「世界禁煙デー」(5月31日)に合わせ、「禁煙宣言」の広告を地元紙に掲載するなどその取り組みを紹介するとともに、喫煙者は非喫煙者と比べコロナ感染率が高くなること示し、知事らに禁煙の大切さを訴えた。
友野印刷からフェースシールド寄贈
県医師会報の印刷など手掛ける友野印刷が6月12日、フェースシールド500枚を県医師会に寄贈。
医師会報6月10日・25日号は合併号
新型コロナウイルス感染症拡大により、県医師会活動は大幅に縮小を余儀なくされたことから6月も合併号(25日発行)に。5月号に続く緊急措置。
<第2次松山正春執行部・2020年6月~2022年6月>
第2次松山執行部は無選挙で全員が留任した。
この期間も、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に全力で臨んだ。
2020年12月、岡山県に「医療非常事態宣言」が発令され、会議、研修なども軒並み中止やWeb開催となった。7月の東京五輪も無観客での開催となった。医師会役員らはPCR検査出務、コロナワクチン夜間集団接種などに奔走した。県医師会と県民が一体となって新型コロナを収束させようというキャンペーン「UNITE FOR SMILE PROJECT」を始動させた。その一環として、冬の夜空に花火を打ち上げ、コロナ収束を願うとともに県民に“元気”をプレゼントした。一方で岡山商工会議所など団体、企業などから医師支援の寄付が相次いだ。松山会長は、コロナの波が起こる節目々々で記者会見を行い、県民へ情報提供とお願いを行った。
- 会長
- 松山正春
- 副会長
- 清水信義、大原利憲
- 専務理事
- 神﨑寛子
- 会計担当理事
- 内田耕三郎
- 常任理事
- 佐藤正浩、合地 明、藤本政明
- 理事
- 國富泰二、田淵和久、太田隆正(備中ブロック選出)、大橋 基(備前ブロック選出)、宮本 亨(美作ブロック選出)、石井純一(岡山ブロック選出)、平木章夫(倉敷ブロック選出)、榊原 敬、名越 充、尾﨑敏文
- 監事
- 中島豊爾、松下 睦

第2次松山執行部
<日本医師会 新会長に中川俊男氏> 6月27日開かれた第147回日本医師会代議員会の会長選挙で、中川俊男副会長が横倉義武会長を破り、新会長に選出。
県医師会が県健康づくり財団へPCR検査機器贈る(7月)
県医師会は7月14日、岡山県健康づくり財団へPCR検査機器1台と自動核酸抽出装置1台を寄贈。
「PCR検査は今一番必要とされているので、機器を贈った」と贈呈式で清水副会長。5月に岡山南RCから贈られた寄付金1千万円を原資に購入した。
県医師会が熊本県医師会へ見舞金(7月)
県医師会は7月17日、7月豪雨で人吉市などの医療機関が甚大な被害を受けたことから、熊本県医師会へ見舞金100万円贈る。松山会長が熊本県医師会館を訪れ、「犠牲者のご冥福をお祈りします。2年前の西日本豪雨災害による真備の水害ではお世話になりました」と、福田稠同会長に手渡した。
松山会長が紙面批評「山陽新聞を読んで」執筆開始(7月)
松山会長の山陽新聞の記事を論評する「山陽新聞を読んで」の掲載が、7月26日から始まる。初回はハンセン病患者に対する偏見と差別を報じた記事を取り上げ、「新型コロナ感染者への誹謗・中傷はこれと同様の構造。90年前と変わらない」と指摘した。2022年5月22日まで、ほぼ2年(2カ月に1回)にわたり担当した。
県医師会が津山中央病院へPCR検査機器寄贈(8月)
新型コロナ感染拡大でPCR検査機能の強化が喫緊の課題となっていることから、県医師会は8月25日、県北の基幹医療機関である津山中央病院へPCR検査機器一式を寄贈。
石川 紘前県医師会長に三木記念賞(8月)
石川 紘前県医師会長が、岡山県の医療界に多大な貢献をしたとして第53回岡山県三木記念賞を受賞。氏は四半世紀近く県医師会の役員を務めるなど岡山県の医療界を牽引した。8月31日、岡山市のルネスホールであった授賞式で伊原木知事から賞状・賞金が贈られた。
TV特番「がん撲滅を目指して~検診で早期発見を~」放送(9月)
県医師会は県健康づくり財団と共同で、TV特番「がん撲滅を目指して~検診で早期発見を~」を9月21日、RSKテレビで放送した。9月のがん征圧月間の一環。大原利憲副会長と西井研治県健康づくり財団附属病院長が出演、「コロナ禍でがん検診の受診者が激減しているが、早期発見のため必ず検査を」と訴えた。なお、この年の「がん征圧岡山県大会」は中止。
第2回新型コロナウイルス感染症対策講演会(9月)
県医師会は9月13日、第2回の標記講演会を県医師会館三木記念ホールで開いた。講師の西嶋康浩岡山県保健福祉部長と日医の釜萢 敏常任理事が、新型コロナウイルス感染症の現状と課題について、それぞれ講演した。
新型コロナ禍での受診調査 9割が収入減(10月)
県医師会が8月に行ったコロナ禍における会員の受診状況(2020年3~6月)をまとめ、会報10月25日号に掲載。受診者数、収入とも大半の医療機関で減少。特に緊急事態宣言が発令された4、5月の落ち込みが著しく、中でも耳鼻咽喉科、小児科が顕著。
日本維新の会が県医師会にマスク寄贈(11月)
岡山県医師会は11月18日、日本維新の会からN-95マスク2700枚の寄贈を受けた。片山虎之助共同代表が県医師会館を訪れ、松山会長に現物を渡した。
OHK「なんしょん?」 県医師会コーナースタート(11月)
県医師会をもっと県民に知ってもらおうと、OHK「なんしょん?」の県医師会レギュラーコーナーが、11月18日スタート。初回は松山正春会長が出演し、県医師会の多彩な活動を紹介するとともに拡大するコロナ感染症(第3波)の県内の状況を解説。改めて“新しい生活様式”の実践を呼びかけた。
「年末は再び外出自粛を」 県医師会が記者会見(第2弾)(11月)
新型コロナウイルス感染者が10月以降急増したのを受け、岡山県医師会は11月27日、県医師会館で記者会見を開いた。松山会長は「病床稼働率は、目下30.5%と予断を許さない状況。高齢者に感染が拡大すれば、医療崩壊の恐れもある」としたうえで「緊急事態宣言時のように緊張感を持ち、年末は改めて行動自粛を」と訴えた。会見は2回目。
岡山県に初の「医療非常事態宣言」(12月)
コロナ感染者の急拡大を受け、伊原木知事と松山県医師会長が12月21日、県庁で臨時記者会見を行い、知事は「岡山県医療非常事態宣言」を発令した。松山会長は「クラスター多発で病床稼働率は65.9%に上昇した。このままでは医療崩壊の恐れがある」と危機感を強める一方、知事は県民に「最大限の行動自粛」を要請、「年末年始は宴会、会食などは中止し、帰省は慎重にしてほしい。クリスマス、正月は家で静かに過ごして」と訴えた。
※2021年2月12日、同宣言は解除
五洋医療器が県医師会へアルコールハンドジェル寄贈(12月)
医療機器・薬剤販売の五洋医療器(本社・福山市)が12月16日、「感染予防に役立てて」と手指消毒用のアルコールハンドジェル600個を県医師会へ寄贈。
岡山商工会議所が県医師会に500万円寄付(12月)
年末年始もコロナと闘う医療従事者を応援したい―岡山商工会議所の松田久会頭は、12月28日県医師会を訪れ、松山会長に支援金500万円を寄付した。浄財は、不休でコロナ患者に対応する医療関係者を支援するため松田会頭が急遽呼びかけ、企業が応えたもの。5月にも400万円の寄付があり2度目。
2021(令和3)年
県内CATV共同企画 新春特番「知事と語る」に松山会長出演(1月)
1月1日に放送された岡山県内のケーブルテレビ(CATV)14社の共同企画・新春特番
「知事と語る 生き活き岡山」に対談者の一人として松山会長が出演、伊原木知事にコロナ感染者、医療従事者やその家族への誹謗・中傷に対し対策を要望した。
福嶋学園が県医師会へ飲料水寄贈(1月)
福嶋学園の福嶋裕美子理事長が1月22日、県医師会館を訪れ松山会長に飲料水1000本寄贈。
ブロンズ像を京都市京セラ美術館に寄贈(2月)
県医師会が所蔵していた彫刻家・菊池一雄のブロンズ像「拱」(高さ175センチ)の京都市京セラ美術館への寄贈が、2月1日付で正式に決まる。同氏は、京都画壇の重鎮・菊池契月の長男。作品は長年、旧衛生会館や新医師会館のロビーに飾られ入館者に親しまれていた。
移動会長室 「医療のかかり方」 初回は津山で(2月)
移動会長室事業の新たに4本目の柱として加わった「医療のかかり方」の初回が2月9日、「正しい薬の飲み方~多剤・重複投与について~」をテーマに津山市で開かれた。岡山県薬剤師会の堀部徹会長らが解説した。
「UNITE FOR SMILE PROJECT」スタート(3月)
医療者と県民が一丸となって新型コロナウイルスを収束させようという県医師会のキャンペーン「UNITE FOR SMILE PROJECT」が3月22日始動した。マスクをつけなくても安心して思いっ切り笑える日を願い、笑顔が繋がった様子をデザイン 新聞に掲載された「UNITE FOR SMILE PROJECT」の告知化したシンボルマークを作成。同日の山陽新聞広告で告知したほか、小冊子を作製し広報した。
丸倉成果・オガマルシェが県医師会に茶葉寄贈(3月)
ごぼう茶で心癒して―農産物加工・製造の丸倉青果(倉敷市)とその販売会社オガマルシェ(同)が3月3日、地元連島産のゴボウ茶100袋を県医師会に寄贈。
岡山村田製作所が県医師会に500万円寄付(3月)
岡山村田製作所(瀬戸内市)が3月10日、県医師会に500万円を寄付。「岡山の地に創業した恩返し。コロナと闘う医療従事者を支援したい」と唐木信太郎社長。
岡山中央LCが県医師会に40万余円寄付(3月)
岡山中央ライオンズクラブが3月16日、チャリティーゴルフの収益金40万6千円寄付。
第8回CKD県民公開講座(3月)
「腎臓と栄養」をテーマに第8回CKD県民公開講座が3月20日、初めてオンラインで開かれた。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事前に参加者を募っての開催となった。
倉敷・連島南小児童からの善意の寄付(3月)
特産のれんこんで作ったグッズで募金した“善意”を送ります-倉敷市立連島南小5生児童が、“れんこん募金”で集めた8万2,923円を3月25日、県医師会に寄付した。同小体育館で行われた贈呈式では、児童代表が松山会長に現金箱などを贈った。会長は「多くの企業、団体などからも寄付・寄贈を頂いているが、今日が一番うれしい」と謝辞を述べ、児童に感謝状と花束を返礼した。
RSKのTV番組「メッセージ」に松山会長出演(3月)
3月31日夜放送のRSKテレビのドキュメンタリー番組「地域スペシャル メッセージ」に松山会長がコメンテーターとして出演。新型コロナの対応に追われた岡山県の医療界をはじめ、スポーツ界、観光業界、飲食業などのこの1年をリポートする中で、松山会長は「第4波を警戒しなければならない。PCR検査体制の強化とともにワクチン接種は、自分を守るだけでなく社会的にも重要。県民がワンチームで立ち向かわなければならない」と力説した。
LC国際協会336-B地区が150万円寄付(4月)
ライオンズクラブ国際協会336-B地区(金礪 毅地区ガバナー)が4月11日、150万円を県医師会に寄付。同日、岡山市で開催された第67回地区年次大会で鳥取県医師会(渡辺 憲会長)とともに松山会長に贈られた。
新型コロナ禍での受診調査(2回目) 大半が収入減(4月)
県医師会が1月に実施した会員の受診状況の2回目調査(2020年7~11月)をまとめ、会報4月10日号に掲載。それによると同期間中の受診者数、収入ともに大半の医療機関が前年同期を下回った。前回同様、耳鼻咽喉科、小児科の減少幅が大きかった。
県医師会代議員会議長に福嶋啓祐氏、副議長に滝澤貴昭氏再選(4月)
第200回県医師会臨時代議員会が4月18日開かれ、任期満了に伴う議長、副議長の改選が行われ、議長に福嶋啓祐氏、副議長に滝澤貴昭氏がそれぞれ無投票で再選された。
高齢者へのコロナワクチン接種控え、県医師会が記者会見(第3弾)(5月)
岡山県医師会は、コロナ感染者が過去最多を更新するなど急激な感染拡大とともに、5月17日から高齢者へのワクチン接種が開始されることを受け、5月7日、記者会見を行った。松山会長は「目下、病床稼働率は70%を超えている」と危機感を示したうえで、「かかりつけ医による個別接種は“文化”であり、最も安心できる」とし、「高齢者は重症化を防ぐため、必ず接種してほしい」と強く呼びかけた。会見は3回目。
※岡山県に「緊急事態宣言」(5月16日~31日)発令
松山会長が東京五輪聖火式参加(5月)
2021年7月に開幕する東京五輪の聖火が岡山県入りした5月19日、点灯セレモニーが岡山城下の段で行われ、トーチ走者の一人として松山会長が参加。会長は、トーチを掲げて「ワクチンを受けよう!」と呼びかけました。
県下に「非常事態宣言」が発令されたことから市中での聖火リレーは中止、走者が聖火をつないでいく“トーチキス”と呼ばれる方式に変更された。会長は前回1964年の東京五輪の聖火ランナー(当時岡大2年生)も務めています。
ガールスカウトからメッセージとシトラスリボン届く(6月)
「医療従事者への感謝の思いが届きますように」―ガールスカウト岡山連盟から県医師会に6月14日、スカウト184人のメッセージとシトラスリボン800個が届く。「命がけで奮闘してくださって 見えない敵といつも闘ってくださって ありがとう」
第201回県医師会定例代議員会開催(6月)
新型コロナウイルス感染が収束しない中、第201回県医師会定例代議員会が6月20日、県医師会館三木記念ホールで開催された。初めて書面による議決権行使を認めた。会場ではマスク着用、席の間隔を空けるなど万全のコロナ対策をとった。令和2年度事業報告、同決算が承認された。
タイオン奨学基金がニトリル手袋60万枚寄贈(6月)
タイオン奨学基金が6月22日、県医師会にニトリル手袋60万枚(1箱100枚入り)を寄贈した。「医療従事者へ感謝の意味を込め提供させていただいた」と藤井大温代表理事。同基金からは昨年5月にもマスク7万枚の寄贈を受けた。
県医師会の「禁煙宣言」新聞広告が銅賞(6月)
世界禁煙デー(5月31日)に合わせ、山陽新聞に掲載した県医師会の「禁煙宣言」が6月24日、岡山広告協会新聞広告賞の銅賞に選ばれた。絵柄は川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科の中村俊介助教が指導する学生たちがデザインした。
コロナ第5波受け、県医師会が記者会見(第4弾)(8月)
新型コロナウイルス感染の第5波が猛威を振るっていることを受け、岡山県医師会は8月31日、記者会見を開いた。松山会長は「感染力が強力なデルタ株により10代、20代、30代の若い世代へ蔓延している。これらの世代のワクチン接種がカギを握っている」として、接種を強く呼びかけた。また、かかりつけ医に自宅療養者への対応を促すため「ガイドブック」を作成、全会員に配布したことも紹介した。会見は4回目。
清水副会長が日本禁煙学会「学会賞」(9月)
清水信義副会長が、呼吸器外科医の立場から長年にわたり禁煙の重要性を啓発してきたとして、9月11日、倉敷市で開かれた第16回日本禁煙科学会学術総会で「学会賞」を受賞した。
RSKテレビで「がん検診を受けよう!」(9月)
9月のがん征圧月間の啓発活動の一環として、県医師会は県健康づくり財団とRSKのテレビ番組「がんの早期発見、早期治療のために~コロナ禍における検診の重要性~」を9月20日放送した。大原副会長と西井院長が出演、コロナ禍で検診が減ったままでいることを指摘、医療機関はコロナ対策を十分しているので、「安心して受診を」とアピールした。
COVID‐19研究会スタート(9月)
「見せよう!かかりつけ医の底力」をキャッチフレーズとした県医師会主催の第1回COVID-19研究会が9月22日始まった。松山会長の音頭で発足、第6波に備え、会員にコロナに関する最新の情報を提供するとともに、その対処法などを学ぶのが狙い。2022年5月25日で終了するまで原則月2回、県内外の著名な専門医らを招きハイブリッド方式で計17回開催。
岡山県医師会に岡山労働局長団体賞(9月)
岡山県医師会は9月29日、令和3年度の安全衛生に係る岡山労働局長表彰式で、団体賞を受賞した。研修会などによる産業医の質の向上、新型コロナのワクチン接種相談センター開設、働き方改革における産業医・産業保健機能の強化に関する改正についての会員への周知などの産業保健活動が評価された。
岡山で全国学校保健・学校医大会(10月)
第52回全国学校保健・学校医大会が10月30日、岡山県医師会の担当で開催された。コロナ禍のためWEB方式となった。松山大会長の挨拶の後、「からだ・こころ」、「整形外科」など5つの分科会で研究成果が発表された。日本医師会会長表彰、川崎医科大の中野貴司教授の基調講演、シンポなどのほか、特別講演として、大原美術館の大原謙一郎名誉館長が「大原美術館で見付けてほしいこと」と題して話した。
1年ぶり「けんこう長寿教室」再開(11月)
移動会長室事業の一つである「けんこう長寿教室(栄養編)」が、11月2日総社市西阿曽で開かれた。コロナ禍で一時中止となっていたが、1年ぶり開催で犬飼道雄先生が講演。片岡総社市長、同地区の「百歳体操」グループらが参加した。
“オータムナイト接種”始まる(11月)
県医師会は11月4日、県に協力しコロナワクチンの “オータムナイト接種”を県医師会館特設会場でスタートさせた。若い世代のコロナワクチン接種率が低いことから、「仕事帰りでも接種できます」と、木・金曜日の午後7時半から同9時まで受け付け。初日は伊原木知事が視察に訪れた。保護者同伴の10代も多く、計113人が来場した。
同接種はその後、運営日を金・土曜日、名称を“ワクチンナイト接種”と変更して今日まで継続、2023年3月で終了するまで約2万5000人が接種した。
「第6波に備えて」 県医師会が記者会見(第5弾)(12月)
新型コロナの第5波が収束した一方、新たにオミクロン株が確認されるなど新たな流行が懸念されるとして、県医師会は12月17日、県医師会館で記者会見を行った。松山会長は、「年末年始を控え、第6波が懸念される。県内でオミクロン株がいつ確認されてもおかしくない。ぜひ3回目のワクチン接種を受けて」を訴えた。新聞、TVなど13社が出席。会見は5回目。
2022(令和4)年
冬の夜空に医師会花火1800発!(1月)
県医師会が展開している「UNITE FOR SMILE PROJECT」の一環として、冬の花火が、1月15日午後6時40分から岡山市東区中島の百間川河川敷など3カ所で打ち上げられた。その数、約1800発。コロナ収束とコロナ禍の県民に“元気”と“笑顔”をプレゼントしようと企画。クラウド・ファンディングで寄付を募集、269人から温かい善意が届いた。招待者や地域住民らは “光のスペクタクル”を堪能した。
“県民に元気を”と打ち上げられた花火
第13回県民公開医療シンポジウム(2月)
「新型コロナウイルス感染症とその後の医療を考える」をテーマとした第13回県民公開医療シンポジウム(岡山県医師会・岡山県病院協会共催)が2月23日、県医師会館三木記念ホールでWEB開催された。松下睦倉敷中央病院副院長、中野貴司川崎医科大学教授、大原利憲副会長、藤本政明常任理事が登壇、発言した。日本医師会の江澤和彦常任理事が「新型コロナウイルス感染症を振り返る」と題して、基調講演した。
県民共済が県医師会へ寄付(2月)
県医師会は2月26日、県民共済から100万円の寄付を受けた。山﨑修理事長は「オミクロン株が猛威を振るう中、医療関係者のお役に立ててほしい」と述べ、松山会長は「有効に活用させていただく」と返礼した。
※ロシアがウクライナに侵攻(2月24日)
子ども予防接種 メディアで啓発(3月)
「子ども予防接種週間」(3月1~7日)にちなみ、県医師会は、啓発活動として2月上旬から3月7日まで、岡山駅通路にサイネージ掲載やWEBサイトで情報発信。「コロナ禍ですが、子ども予防接種は不要不急のものではありません。ワクチン接種で防げる病気を防ぎましょう」と訴えた。
RSKラジオ「岡山県医師会 地域医療を支えて」放送(3月)
中国四国9県の局を結んで放送されるRSKラジオ番組「中四国ライブネット」が、「岡山県医師会 地域医療を支えて」をテーマとして、3月13日午後6時から放送された。松山会長、田淵理事、大橋理事、名越理事が出演、それぞれ「コロナと県医師会の対応」「子宮頸がんとワクチン接種」「ACP」「健康寿命を伸ばそう」のテーマで、2時間にわたり話した。
「女性の健康週間 県民公開講座」(3月)
県医師会女医部会が中心となって企画した「女性の健康週間 県民公開講座」が3月13日、県医師会館三木記念ホールで開催された。岡山大学眼科の木村修平講師が「白内障」について、岡山済生会病院の成田亜希子診療部長が「緑内障」について、それぞれ講演した。会場、WEB合わせて約330人が参加。
第9回CKD(慢性腎臓病)県民公開講座(3月)
第9回CKD(慢性腎臓病)県民公開講座が3月21日、県医師会館三木記念ホールでハイブリッド方式で開かれた。テーマは、「腎臓を守る生活習慣 コロナ時代の注意点」。津山中央病院内科部長・透析センター長の堀家英之氏、重井病院管理栄養士の黒住順子氏、県薬剤師会学術委員会委員長の板野円香氏の3講師が講演した。
「第7波の入り口」で県医師会が記者会見(第6弾)(4月)
新型コロナ感染流行の「第7波の入り口」を迎えたとして、岡山県医師会は4月8日、県医師会館で記者会見を行った。松山会長は、「3回目接種は、若い世代で低迷している」として、接種を強く呼びかけた。特に、副反応の懸念から低迷している小児への接種に関して、國富泰二理事が「5~11歳児への接種は、12歳以上と同様に意義がある」との小児科部会の確認事項を紹介した。そのうえで、松山会長は「基本的には推奨しているが、『努力義務』ではなく、保護者が納得した上で判断してほしい」と呼びかけた。会見は6回目。
松山会長 3選果たす(4月)
第202回岡山県医師会臨時代議員会が4月17日開かれ、無投票で現職の松山正春会長が3選を果たした。副会長に大原利憲氏、神﨑寛子氏、理事10人、地区選出理事(5人)などがいずれも無投票で決まった。
スポーツ県民公開講座(4月)
岡山県医師会スポーツ県民公開講座が4月24日、県医師会館三木記念ホールで開かれた。岡山大学病院リハビリテーション学部の千田益生教授による「知らないと損する『要介護にならない方法』」の講演などがあった。
新型コロナワクチン“ナイト接種” 1万人達成(6月)
県医師会が運営している新型コロナワクチンの“ナイト接種”が、6月4日(土)午後7時43分、1万人を達成した。保護者とともに訪れた13歳の中学2年生の女子。松山会長から記念の賞状とグッズが贈られた。
<第3次松山正春執行部・2022年6月~2024年6月>

松山正春会長率いる第3次の執行部が、2022年6月19日正式に発足した。4月の第202回岡山県医師会臨時代議員会での会長選挙で3選を果たしていた。
松山会長は「県医師会の事業拡大に対応し、常任理事を増員し業務の深化を目指す。また、各部会、研究会の成果を記録として残し、後世に寄与したい」と3期目の抱負を述べた。
副会長は清水信義氏が退任し、大原利憲氏は留任、新たに神﨑寛子氏が就任した。専務理事には内田耕三郎氏。
この期も2023年の県医師会の新年祝賀式は中止となるなど、依然コロナ感染は収束せず、流行の波は9波を迎えた。記者会見は、都合9回にも及んだ(2020年4月~2023年8月)。
2023年5月8日、国の判断で新型コロナが「5類」に移行したことから、次第に経済活動が活発化、コロナ前にほぼ戻った。移動会長室も再開した。9月には「第30回全国医師会共同利用施設総会」が岡山県医師会の担当で開催され、成功裏に終了した。
- 会長
- *松山正春
- 副会長
- 大原利憲、*神﨑寛子
- 専務理事
- *内田耕三郎
- 会計担当理事
- *佐藤正浩
- 常任理事
- 合地 明、宮本 亨(美作ブロック選出)、榊原 敬、*楢原幸二、*山田 斉
- 理事
- 田淵和久、太田隆正(備中ブロック選出)、大橋 基(備前ブロック選出)、平木章夫(倉敷ブロック選出)、*木村 丹(岡山ブロック選出)、*岡 茂、*増山 寿、*宮本宣義
- 監事
- 中島豊爾、松下 睦
(*は新任)

<日本医師会 新会長に松本吉郎氏> 6月25日開催の定例代議員会で任期満了に伴う役員選挙を行い、松本吉郎常任理事が、松原謙二副会長を破り、新会長に初当選した。現職会長の中川俊男氏は不出馬。江澤和彦常任理事は3選。
第一エンタープライズから100万円(8月)
「新型コロナと闘っている医療者を支援したい」と不動産賃貸業の第一エンタープライズ(岡山市)から8月24日、県医師会へ100万円の寄付があった。
3年ぶり「がん征圧岡山県大会」(8月)
新型コロナ感染拡大のため過去2年中止になっていた「がん征圧岡山県大会」が、8月29日、県医師会館三木記念ホールで開催された。松山会長は「コロナ禍でがん検診の受診者が減っている。死亡者を減らすには早期受診、早期治療が重要であり、がん検診は不要不急のものではない」と訴えた。
RSKテレビ「がん検診を受けよう!」(9月)
9月のがん征圧月間の啓発活動の一環として、県医師会は県健康づくり財団と共同でRSKテレビの「がん検診を受けよう!~早期発見、早期治療のために~」を9月19日放送した。大原副会長と西井院長が出演した。
コロナ感染者の全数把握簡略化で記者会見(第7弾)(9月)
新型コロナ感染者の全数把握が9月26日から簡略化されるのを受け、県医師会は同日、記者会見した。松山会長は「全数把握簡略化は、医療機関の事務負担軽減につながる一方で、届け出対象外の人たちが自宅療養中、容体が急変した際の対応が懸念される」とし、自宅療養者のサポートセンターに相談する仕組みを周知徹底することが大切とした。そのうえで「かかりつけ医は患者さんを見放すことはありません」と力説した。在岡マスコミ12社が参加。コロナ流行後、会見は7回目。
久米郡医師会が解散(9月)
久米郡医師会は2022年9月30日をもって解散した。「会員の減少による減収とコロナ禍での活動制限などで会の運営が行き詰まった」(岩本博通元同医師会長)。久米郡医師会は1947年発足、2005年の市町村合併により旧久米郡久米町が津山市に編入されたことで、医師会会員の減少に拍車がかかったうえ、高齢化による退会や閉院があり、ここ数年は5医療機関(久米南町2、美咲町3)、会員7人となっていた。会員は2023年3月末まで契約業務を遂行、4月1日から津山医師会の所属となる。
松山会長に旭日小綬章(11月)
11月3日発表された2022年秋の叙勲で、松山正春会長が長年にわたる医師会活動などの功績により旭日小綬章を受章した。
RSK「いまドキッ!」県医師会コーナースタート(11月)
RSKテレビの情報番組「ライブ5時 いまドキッ!」県医師会コーナーが、11月9日スタートした。初回は松山会長が出演、県医師会の多岐にわたる活動について紹介した。
県医師会コーナーは、広報活動の一つとして、医療の様々なテーマについて、役員が分かりやすく解説する。OHK「なんしょん?」の同コーナーと隔月ごとに放送。
2023(令和5)年
松山会長、知事と合同記者会見(1月)
新型コロナの第8波に急拡大を受け、松山会長が、伊原木知事と1月12日、県庁で合同記者会見した。知事は「2番目に深刻な『レベル3』に引き上げる」と宣言する一方、松山会長は「オミクロン株対応ワクチン接種は、65歳以上でも60%に留まっている。ぜひ5回目の接種を」と呼びかけた。
令和5年県医師会新年祝賀式中止(1月)
1月14日に予定されていた県医師会新年祝賀式は、オミクロン株コロナ感染者急増(第8波)を受け、中止に。3年連続。
県医師会と県警が合同防犯訓練(2月)
県医師会と県警の合同防犯訓練が2月15日、診療所を訪れた不審者が、「早く診ろ」と、ナイフを取り出し騒ぐという想定で、岡山市の神崎皮膚科で行われた。“異常”を察知した院長が110番通報するとともに、患者、職員を避難誘導して身の安全を確保する―という手順を確認した。
近年、医師や診療所を狙った凶悪犯罪が相次いだことから実施した。
子ども予防接種 メディアで啓発(3月)
「子ども予防接種週間」(3月1~7日)にちなみ、県医師会は、啓発活動としてメディアのサイトにバナー広告掲載や情報提供を行い、ワクチン接種を呼びかけた。
県医師会に入会サポートデスク開設(4月)
郡市等医師会、県医師会、日本医師会への入会・退会・異動・変更手続きを代行する「入会サポートデスク」を県医師会に開設、4月1日から運用開始。日本医師会組織強化を目指し、病院診療所開設者、勤務医、研修医が入・退会等を簡便にできるようにした。
福嶋代議員会議長、滝澤同副議長が3選(4月)
4月6日開かれた第204回県医師会臨時代議員会で任期満了に伴う代議員議長、同副議長の回線が行われ、福嶋代議員会議長、滝澤同副議長がそれぞれ3選を果たした。また、組織強化策として、医師会入会費が医学部卒後5年まで無料となったことを受け、会費・入会金徴収規程の改正が上程され、承認された。
新型コロナ「5類」移行で記者会見(第8弾)(5月)
新型コロナウイルス感染症が2023(令和)年5月8日から感染法上、2類相当から5類に移行したことを受け、県医師会は同月15日記者会見を行った。松山会長は「法的には変わってもウイルスが消滅したわけではない」としたうえで、「第8波では、コロナによる死亡者のうち70歳以上が96%を占め、高齢者には危険は感染症」と指摘、「高齢者施設や医療機関受診ではマスクは必須」と改めて強調した。コロナ関連の記者会見は8回目。
県医師会と岡山県警・津山署が津山の診療所で不審者対応訓練(5月)
県医師会と岡山県警・津山署が5月26日、津山市二宮の「わたなべ内科医院」で不審者対応訓練を行った。今年2月の岡山市の医療機関で次いで2回目、県北では初めて。
第205県医師会定例代議員会(6月)
第205回県医師会定例代議員会が6月18日、県医師会館三木記念ホールで開かれ、令和4年度事業の報告、同決算を承認した。また、定款施行規則の一部改正(解散した久米郡医師会を削除)も承認された。代議員からは医療DX推進に関し、急速な導入に懸念が表明される一方、導入には国が規格を標準化することや費用補助を要望する意見が相次いだ。
県医師会が「新型コロナ第9波に入った」として記者会見(8月)
岡山県医師会は8月3日、県医師会館で記者会見を開いた。新型コロナは5月8日から5類に移行し3カ月が経過。松山会長は、「社会活動はコロナ前に戻った感がある一方で、定点把握の数字を見ると、第8波の11月上旬とほぼ同水準で、第9波に入ったとみていい」との認識を示し、改めてマスク着用、手指消毒などの基本対策を呼びかけた。また、県医師会の取り組みとして、県内1,463の高齢者施設を対象とした緊急時相談窓口を開設、8月9日から運用を開始するとした。コロナ関連の記者会見は9回目。
医療機関向け防犯講習会(8月)
県医師会と岡山県警本部の共催で医療機関向け防犯講習会が、8月31日、県医師会館三木記念ホールで行われ、医療関係者94人が受講した。県警本部の担当者が、防犯カメラや非常通報装置の設置などハード面と防犯マニュアル作成、職員の教育・訓練などソフト面の防犯対策の必要性を説明した後、刺股を使って不審者への対応を実践した。
令和5年度「がん征圧岡山県大会」開催(9月)
令和5年度「がん征圧岡山県大会」(岡山県・岡山県医師会・岡山県健康づくり財団主催)が9月4日、岡山市の県医師会館三木記念ホールで医療関係者、愛育委員など約300人が参加して行われた。新型コロナが「5類」に移行したことで、入場制限なしでの大会。がん征服者事業功労者への感謝状、がん研究の助成金授与などが行われたほか、岡山済生会総合病院の高畑隆臣診療部長が「胃がんと向き合うため」と題して講演した。
がん征圧月間で県医師会がTV特番(9月)
9月のがん征圧月間の啓発行事の一環として、県医師会は岡山県健康づくり財団と共同で同月18日、山陽放送で「受けよう!がん検診~早期発見と早期治療のために~」を放送した。大原利憲副会長が出演し、岡山県のがん疾患の状況など説明した上で、検診の大切さを強調するとともに、県内の中山間地や島しょ部の集団検診の様子などを紹介した。
第30回全国医師会共同利用施設総会が岡山で開催(9月)
「次代に託す医師会共同利用施設の使命」をテーマとして第30回全国医師会共同利用施設総会が9月9、10日の両日、岡山県医師会の担当で岡山市のコンベンションセンターで開催され、全国から約400人が参集した。来賓として伊原木隆太県知事、大森雅夫岡山市長、日本医師会からは松本吉郎会長、角田徹副会長らが出席した。
初日は、松本会長の講演、3つの分科会で共同利用施設の運営状況の報告の後活発な意見交換が行われた。岡山県からは、赤磐医師会病院の取り組み、新見医師会の介護老健施設「くろかみ」と地域包括ケアについて、それぞれ代表者から発表があった。2日目は、岡山県の3つ共同利用施設(赤磐医師会病院、岡山市医師会総合メディカルセンター、新見医師会の老健施設「くろかみ」)を映像で紹介した。閉幕後、参加者は、それぞれ赤磐医師会病院と岡山市医師会総合メディカルセンターを見学した。

岡山市で開催された第30回全国医師会共同利用施設総会の開会式で
挨拶する松山会長
RSKラジオで医師会コーナー始まる(10月)
RSKラジオの情報番組「天神ワイド 朝」(9:20~30) の県医師会コーナー「からだにいい話」が、10月11日スタート。OHKの「なんしょん?」、RSKのTV「いまドキッ!」に次ぐ、メディアによる県医師会の広報活動。初回は、松山会長が出演、県医師会の活動を紹介した後、ACPをテーマに解説した。
同コーナーは、隔月で第2水曜日に放送。県医師会の役員が健康・医療について、話題を提供する。
県医師会が岡山県警察と防犯協定締結(11月)
県医師会は岡山県警察と11月7日、防犯協定を締んだ。県警本部庁舎で行われた調印式では、松山会長と荻野英俊生活安全部長が協定書に署名した。協定では、県医師会及び会員の医療機関は、平素から県警と連携・協力するとした上で、①県警は、医療機関の犯罪防止とサイバー攻撃を受けた場合などに迅速・適正に対応する、②医療機関は、地域の「安全・安心」のため、防犯ポスターの掲示など啓発活動に協力する―としている。
近年、医療機関を狙った放火殺人や医師らを銃殺する凶悪犯罪が相次いだことから、これまで県医師会と県警は連携して、不審者対応訓練や防犯講習会を開いていた。
令和5年度岡山県医師会長賞にOCITなど3団体(11月)
令和5年度岡山県医師会長賞が、11月8日開かれた理事会で、岡山県クラスター対策班(OCIT)▽倉敷医師会女性の会▽新見市在宅医療・介護連携推進協議会の3団体に贈ることが決まった。表彰式は、12月9日、岡山県医師会館三木記念ホールで行われた。
地域医療貢献表彰を創設(11月)
開業25年と50年を迎えた会員を顕彰する「地域医療貢献表彰」の表彰式が11月8日、岡山市のANAクラウンプラザホテル岡山で行われ、その功績と労を称えた。晴れの受賞者は、初回とあって25年以上の計440人。表彰式では、都合で欠席となった松山会長がビデオメッセージで「地域で黙々と、真摯に医療に向き合ってきた先生方に敬意と感謝を申し上げる。今後も地域医療を支えて頂きたい」と祝福した。受賞者を代表して近藤洋一先生(ヒゴヤ内科、御津医師会)が、「日々、診療をしているうちに50年以上が過ぎた。県医師会のお陰で厚労大臣表彰なども頂き、この恩は忘れない」と謝辞を述べた。
この賞は、毎年開業25年と50年を迎える会員を対象として、松山会長の発議で今年新たに設けられた。
物価高騰で医療機関支援を県に要望(11月)
国の経済対策として物価高に対する重点支援地方交付金が追加されることを受け、松山会長は11月29日、岡山県の梅木和宣保健医療部長を訪ね、医療機関に重点配分されるよう要望書を提出した。会長は「光熱費の高騰などが医療機関の経営を圧迫している。医療は診療費に転嫁できないという特殊事情を考慮して、配分をお願いしたい」と訴えた。
12月1日にも上坊勝則副知事を訪ね、重ねて要望をした。
「国民医療・介護を守るための総決起大会」(12月)
物価高などで医療経営を圧迫する中、来年度の診療報酬・介護報酬・福祉サービス報酬のトリプル改定を控えて「国民医療・介護を守るための総決起大会」が12月6日午後7時30分から岡山県医師会館三木記念ホールで地元選出国会議員ら約400人が参加して行われた。県医師会、県病院協会、県歯科医師会など参加団体の代表者が決意表明、「物価高、人材確保への対応、医療DX推進には十分な原資が必要。適切な財源確保を要望する」という決議文を採択した。
2024(令和6)年
能登半島地震でJMATおかやま第1陣出発(1月)
1月1日に発生した能登半島地震の被災地支援のため県医師会が編成した「JMATおかやま」の第1陣が、1月19日、石川県に向け出発した。赤磐医師会の吉井チーム(吉井莊哲医師、看護師2人、ロジ1人の4人編成)。
午前8時40分、医師会館1階で行われた出発式で、松山会長は、「まず自身の安全を最優先してほしい。被災者に寄り添った支援をお願いしたい。避難所では災害関連死を出さないことが大事だ」と激励し、吉井先生は「普段、診療するのと同じ気持ちで参ります」と答え、新幹線に乗り込んだ。医薬品等の携行品は、県医師会職員が事前に金沢駅駐車場に搬送しており、引き継いだ。
同チームは、まず石川県庁に設置された「石川県JMAT調整本部」に赴き、指示を受け、県庁内の「JMAT金沢以南調整支部」に配属された。同月22日まで当地に滞在、先遣の徳島JMATとともにエリアの避難所の状況や医療ニーズの情報収集、新規JMAT隊への活動指示などの業務に当たった。

能登半島地震被災地へのJMATおかやま第1陣「吉井チーム」=令和6年1月19日、県医師会館

各支部をwebで結んでのJMAT本部連絡会議=石川県庁舎
能登半島地震 JMATおかやま活動報告の記者会見(2月)
石川県でのJMATおかやまの医療支援活動が一旦終了したことから岡山県医師会は、2月26日岡山県医師会館で記者会見を開き、派遣したチームの活動を報告した。1月19日の第1陣から2月24日の第12陣まで継続して、医師、看護師、薬剤師、事務の計48人を派遣。会見では「小林チーム」の小林孝一郎氏が、石川県庁に設置された「JMAT金沢以南調整支部」での統括業務などについて、レポートした。その中で、「2次避難所の避難者は、ホテル・旅館の個室にいるため健康状態の把握が難しく、心肺停止事案が2件あった」と指摘、患者情報を共有し、対応する仕組みを作ることが課題とした。
役員改選で松山会長4選(4月)
任期満了に伴う次期役員を選出する第206回岡山県医師会臨時代議員会が4月28日開かれ、現職の松山正春会長が4選を果たした。大原利憲、神﨑寛子両副議長は再選、理事・地区選出理事15人が決まった。監事は、中島豊爾氏に代わって清水信義氏が新たに選出された。
いずれも立候補者は定数通りで、無投票で決まった。新執行部は6月開催の定例代議員会終了後、正式発足する。任期は令和8年6月の定例代議員会終了までの2年間。
新興感染症に関する提言書を知事に提出(5月)
岡山県医師会や疫学専門家などで構成する「新興感染症に対する医療提供体制調整検討協議会」を代表して松山正春県医師会長、神﨑寛子同副会長、頼藤貴志岡山大学教授が2024年5月31日、県庁を訪れ、伊原木隆太知事に提言書を提出した。
「情報共有ツールの開発・運営に関する提言書」と「OCITの将来・人材育成検討に関する提言書」の2つ。
同協議会では、新型コロナ禍で組織されクラスター発生の分析、感染対策・感染防止の指導などを行った岡山県クラスター対策班(OCIT)や医療機関同士で構築された連携は、 “レガシー”と評価する一方、問題点も浮き彫りになった。これを受け、来るべき新興感染症流行時に備えるため「協議会」の2つのWGで議論を重ね、このほど提言をまとめた。
提言は以下の通り。
・全県規模の情報共有ツールの開発・運営
今次コロナ禍で、全県規模でのデータ収集や疫学分析を行い、県民や医療機関にリアルタイムでフィードバックするには困難な点があったことから、全県での収集・分析が必要であるとし、新たな情報共有ツールの開発・運営が必要とした。提言では、①行政機関における統一フォーマットの作成と運用に関する対策、②医療機関でのJ-SPEED利用に関する検討、③NESIDや電子カルテなど既存情報利用の促進―を挙げている。
・OCITの将来・人材育成
①疫学分析の推進と分析体制の整備、②感染対策に関わる人材育成、③感染症に関わるネットワークの維持と深化、④ネットワークを利用した感染対策・情報発信の推進、⑤将来の感染症や健康危機管理に対応する組織の検討。
第207回岡山県医師会定例代議員会
標記代議員会が6月16日開かれ、2023年度事業計画の報告、議事として、①2023(令和5)年度決算、②役員報酬の支給規定の一部改正が、それぞれ代議員に諮られ承認された。個人質問では、災害拠点病院での診療受援体制について、▽2023(令和5)年度決算と財務改善策、▽中山間地での遠隔オンライン診療など―の説明が求められた。
代議員会終了後、第4次松山執行部が正式にスタートした。
<第4次松山執行部・2024年6月~>

第4次松山執行部が2024年6月16日、発足した。新任は中山堅吾理事1人。松山会長は「3年にわたるコロナとの戦いも一段落。会長就任以来実施してきた“移動会長室事業”に力を入れていきたい。特に若い世代が生き方を考える契機となるようACPの普及を加速させたい」とした。
監事は、中島豊爾氏が退任、清水信義氏が新たに就任した。
- 会長
- 松山正春
- 副会長
- 大原利憲、神﨑寛子
- 専務理事
- 内田耕三郎
- 会計担当理事
- 佐藤正浩
- 常任理事
- 合地 明、楢原幸二、宮本 亨(美作ブロック選出)、山田 斉、榊原 敬、木村 丹(岡山ブロック選出)
- 理事
- 田淵和久、岡 茂、増山 寿、宮本宣義、太田隆正(備中ブロック選出)、平木章夫(倉敷ブロック選出)、*中山堅吾(備前ブロック選出)
- 監事
- 松下 睦、*清水信義
(*は新任)

松山会長に「杉浦賞最優秀賞」授与(7月)
地域医療に顕著な貢献をした個人・団体を顕彰する「第13回杉浦地域医療振興賞」の授与式が、令和6年7月11日、東京都千代田区の帝国ホテル東京であり、最優秀賞に選ばれた「移動会長室事業で若者世代へACP普及啓発」を主導する松山正春会長に杉浦記念財団の杉浦昭子理事長らから賞状と盾、賞金が贈られた。
式では、松山会長が事業の狙いや活動成果などを発表。「会長就任後、県民の生の声を聞くため『移動会長室』事業を立ち上げ、ACPやフレイル対策などをテーマに県内各地で講座を開いている。6年間で87回、約5000人の方が参加した」とした上で「ACPに関しては、高齢者だけでなく、若い世代への普及に力を入れている。これまで41回開催したが、生徒・学生対象は11回で、『命、生き方について考えさせられた』『家に帰って家族とも話し合いたい』など確かな手応えがあった。20年、30年先を見越した社会の意識醸成を期待している」と、その意義を力説した。
同賞は、東海・首都圏を中心に薬局を展開する「スギ薬局」が設立した公益財団法人杉浦記念財団が主宰。